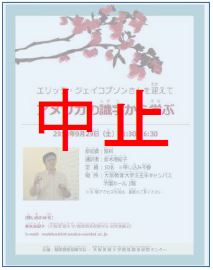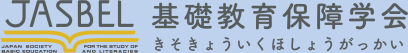トヨタ財団の助成による基礎教育に関する日韓共同プロジェクトの一環で、学習者による共同宣言づくりにむけたワークショップを開催しました。
韓国側31名、日本側は北海道から沖縄まで33名の参加がありました(うち学習者は日韓合計17名)。
関係者のご協力のおかげで、言葉の壁を超えて対話にあふれる3日間となりました。宣言文は今年9月末に韓国で開催される最終シンポジウムで発表されます。


ニューズレター第9号を発行しました。
会員のみなさまは、右下のボタンからダウンロードできます。
パスワードは「入会申込書」の裏面に記載しております。
2019年2月24日に開催された2018年度第1回理事会の記録です。
《審議事項》
1 第4回~第5回研究大会について
2 学会誌について
3 研究委員会の取り組みについて
4 倫理規定検討委員会の取り組みについて
5 役員選挙にむけた「会則改正」、「理事選出規程」について
6 「夜間中学設置推進・充実協議会」への要望書について
7 「夜間中学の防災対応に関する提案」を受けて
8 その他
《報告事項》
1 会員の動静について
2 2018年度第2回常任理事会について
3 全国各地の取り組みについて
4 その他

夜間中学の安全対策に関する要望書を提出しました。
全文を右下のボタンからダウンロードできます。
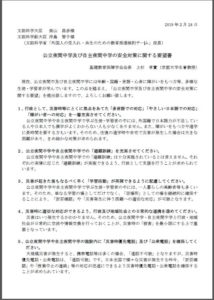
【要望書名】
公立夜間中学及び自主夜間中学の安全対策に関する要望書
【提出先】
文部科学大臣 柴山 昌彦様
文部科学副大臣 浮島 智子様
(文部科学省「外国人の受入れ・共生のための教育推進検討チーム」座長)
【要望内容】
①行政として、災害時等にとくに焦点をあてた「多言語での対応」
「やさしい日本語での対応」「障がい者への対応」を一層充実させてください。
②公立夜間中学や自主夜間中学での「避難訓練」を充実させてください。
③災害が起きた後もなるべく早く「学習活動」が再開できるように配慮してください。
④災害時に適切な対応ができるよう、行政及び地域社会との日常的な連携を進めてください。
⑤公立夜間中学や自主夜間中学の施設内に「災害時優先電話」及び「公衆電話」を確保してください。
教育機会確保法の附則には、「この法律の施行後三年以内にこの法律の 施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等 の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする」とあります。 それを受けて、2018年11月に、夜間中学設置推進・充実協議会が設置されました。
本学会としての要望を座長に提出しました。
要望理由も述べた全文は添付ファイルをごらんください。
【要望内容】
①車椅子利用者等も夜間中学に入学できるようにして下さい。
②学齢超過の夜間中学生にも就学援助の申請資格を与えて下さい。
③スクールバスや福祉タクシー活用等により、スムーズに通学できるようにして下さい。
④各都道府県の「協議会」設置を義務化するとともに夜間中学設置を促進する組織にして下さい。
⑤義務教育相当の学力に関する「識字調査」を実施して下さい。
⑥夜間中学生の多様性を踏まえ夜間中学の教職員配置数を抜本的に改善して下さい。
⑦夜間中学にスクールカウンセラーやソーシャルワーカーを十分配置して下さい。
⑧大学の教職員養成課程や現職の教職員研修に夜間中学や不登校に関連した内容を盛り込んで下さい。
⑨義務教育相当の学習支援を行う自主夜間中学等の民間団体の活動が支障なく実施できるよう 公共施設使用の際の「減免措置」等の行政による支援を一層充実させて下さい。 また、利用施設のエレベーター設置等によるバリアフリー化を促進してください。
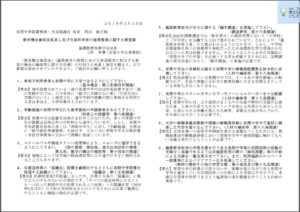
「基礎教育保障学会ニューズレター」第8号を発行しました。
会員のみなさまは、右下のボタンからダウンロードできます。
パスワードは、「入会証明書」の裏面の「ご利用案内」に記載してあります。
2018年11月4日に開催された2018年度第1回常任理事会の記録です。
《審議事項》
1 9月2日総会について
2 第3回~第5回研究大会について
3 学会誌について
4 研究委員会の取り組みについて
5 倫理規定検討委員会の取り組みについて
6 役員選挙に向けた「会則改正」について
7 謝金支出の内規について
8「夜間中学の防災対応に関する提案」を受けて
9 その他
《報告事項》
1 会員の動静について
2 ホームページについて
3 2018年度役員会予定について
4 全国各地の取り組みについて
5 その他

「基礎教育保障学会ニューズレター」第7号を発行しました。
会員のみなさまは、右下のボタンからダウンロードできます。
パスワードは、「入会証明書」の裏面の「ご利用案内」に記載してあります。
2018年9月1日に開催された2017年度第2回理事会の記録です。
<審議事項>
1 総会(9月2日)について
2 第3回研究大会について
3 学会誌について
4 研究委員会の取り組みについて
5 第4回研究大会について
6 その他
<報告事項>
1 会員の動静について
2 学会ホームページについて
3 6月29日総務省との懇談報告(2020年国勢調査「教育綱目」改善のお願い)
4 2018年度第1回常任理事会について
5 全国各地の取り組みについて
6 その他

日韓基礎教育プロジェクト(トヨタ財団助成)の学びあい交流事業が無事に終わりました。昨年12月の大阪に続いて二回目です。
今回は日本から合計19名で訪韓しました。来年3月の福岡での日韓基礎教育宣言づくりワークショップを見越して、「よみかき教室ふくおか」から学習者3名とスタッフ3名も参加してもらいました。
韓国側のみなさんの丁寧かつ心のこもった準備のおかげで、教室訪問2ヶ所、日韓合同プロジェクト会議、実務会議、研究者や政府関係者も交えての合同学習会、学習発表会とたいへん充実した内容でした。学習者同士の交流もあり、「来年、福岡でお待ちしてます」とお別れしました。


写真は、全国文解・基礎教育協議会主催の学習発表会「識字ひろば2018~文解、わたしを踊らせる~」を見学した際の集合写真。文解とは、識字のことですが、文化を読み解き、文化を解放するという意味が込められています。年一度、韓国全土から文解(識字)教室が集います。その人数に驚き、発表に感動しっぱなしでした。
2018年8月31日(金)に第4回日本側プロジェクト定例会議を開催しました。会議の記録を右下のボタンからダウンロードできます。
【会場】首都大学東京 5号館142教室
【日時】2018年8月31日(日)18:00~20:30
【議題】
①経過報告
②第2回学びあい交流会のスケジュール確認
③ブックレット事業の進捗状況報告
④教材翻訳事業の進捗状況報告
⑤日韓基礎教育宣言づくりワークショップ
⑥タイ・バンコクでのユネスコ主催のイベント参加について
⑥最終シンポジウムについて(2019年秋・韓国)
2018年度の役員は以下の通りです。
※敬称略、五十音順
| 役職 | 氏名 | 所属 |
| ━常任理事会━ | ||
|---|---|---|
| 会長 | 上杉孝實 | 京都大学名誉教授 |
| 副会長 | 岡田敏之 | 京都教育大学 |
| 野山広 | 国立国語研究所 | |
| 森実 | 大阪教育大学 | |
| 事務局長 | 関本保孝 | 元夜間中学校教諭 |
| 事務局次長 | 添田祥史 | 福岡大学 |
| 常任理事 | 岩槻知也 | 京都女子大学 |
| 新矢麻紀子 | 大阪産業大学 | |
| 長岡智寿子 | 国立教育政策研究所 | |
| 藤田美佳 | 奈良教育大学 | |
| ━理事会━ | ||
| 井口啓太郎 | 国立市公民館 | |
| 石井山竜平 | 東北大学 | |
| 石川敬史 | 十文字学園女子大学 | |
| 岩槻知也 | 京都女子大学 | |
| 上杉孝實 | 京都大学名誉教授 | |
| 岡田敏之 | 京都教育大学 | |
| 河合隆平 | 金沢大学 | |
| 工藤慶一 | 北海道に夜間中学をつくる会 | |
| 坂本旬 | 法政大学 | |
| 新矢麻紀子 | 大阪産業大学 | |
| 関本保孝 | 元夜間中学校教諭 | |
| 添田祥史 | 福岡大学 | |
| 長岡智寿子 | 国立教育政策研究所 | |
| 野山広 | 国立国語研究所 | |
| 藤田美佳 | 奈良教育大学 | |
| 森実 | 大阪教育大学 | |
| ━委員会━ | ||
| ■学会誌編集委員会 | ||
| 委員長 | 長岡智寿子 | 国立教育政策研究所 |
| 副委員長 | 石川敬史 | 十文字学園女子大学 |
| 委員 | 坂本旬 | 法政大学 |
| 棚田洋平 | 部落解放・人権研究所 | |
| ■研究委員会 | ||
| 委員長 | 森実 | 大阪教育大学 |
| 副委員長 | 新矢麻紀子 | 大阪産業大学 |
| ■研究大会委員会 | ||
| 委員長 | 岩槻知也 | 京都女子大学 |
| 副委員長 | 井口啓太郎 | 国立市公民館 |
| 藤田美佳 | 奈良教育大学/奈良市立月ヶ瀬公民館 | |
| 委員 | 仲江千鶴 | 昭和女子大学大学院博士課程(社会人) |
| ■倫理規定検討委員会(新設置) | ||
| 委員長 | 野山広 | 国立国語研究所 |
| 副委員長 | 新矢麻紀子 | 大阪産業大学 |
| 委員 | 上杉孝實 | 京都大学名誉教授 |
| 岡田敏之 | 京都教育大学 | |
| 添田祥史 | 福岡大学 | |
| 長岡智寿子 | 日本女子大学 | |
| 藤田美佳 | 奈良市立月ヶ瀬公民館 | |
| ━顧問━ | ||
| 見城慶和 | えんぴつの会(元夜間中学校教諭) | |
| 小林文人 | 東京学芸大学名誉教授 | |
| 山田泉 | にんじんランゲージスクール(元法政大学) | |
| ━監事━ | ||
| 鈴木章之 | 田園調布学園大学 大学院院生(社会人) | |
| 松田泰幸 | 町田市中央公民館 | |
| ━会計━ | ||
| 庄司匠 | 夜間中学校と教育を語る会 | |
講師のエリック・ジェイコブソンさんの体調不良より、2018年9月29日(土)に大阪教育大学天王寺キャンパスで開催予定だった公開学習会を中止いたします。