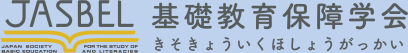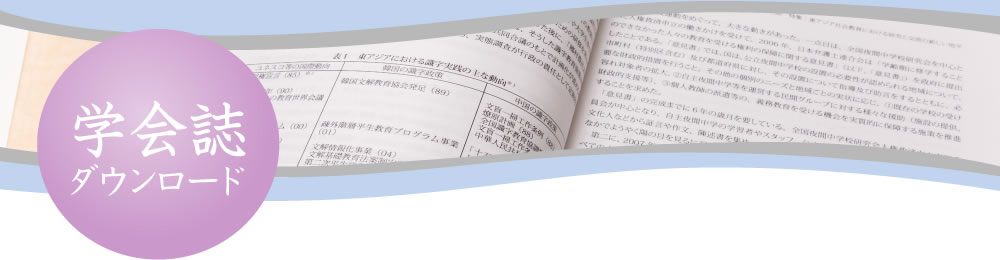
『基礎教育保障学研究』第6号へ投稿される際には、右下のボタンからワードファイルの書式(投稿用原稿のフォーマット)をダウンロードしてお使いくださると便利です。上下余白、行数、文字数、フォントなどがあらかじめ設定されています。原稿執筆時には、必ず執筆要項も熟読してください。
『基礎教育保障学研究(The Journal of the JASBEL)』原稿執筆要項(改訂版2021.11)は、右下のボタンからダウンロードできます。
応募の際は、原稿執筆要項を熟読し、上下余白、行数、文字数、フォント、図表、引用などの定められた様式を遵守してください。
電子ジャーナル ISSN 2433-3921
『基礎教育保障学研究』 第5号を刊行しました。右下のボタンからダウンロードできます。
記事の個別ダウンロードはこちらをご活用ください。(J-STAGE)
-212x300.jpg)
【特集】「基礎教育保障とメディア情報リテラシー」について
<展望論文> 坂本旬(法政大学)
基礎教育保障としての批判的デジタル・インクルージョン:ディスインフォデミック への対応を中心に
<研究論文> シン・テソプ(東義大学)
/翻訳:呉世蓮(早稲田大学)・監訳:肥後耕生(豊岡短期大学)
韓国におけるメディア情報リテラシーの現状と諸問題
<研究論文> 西村寿子(NPO法人FCTメディア・リテラシー研究所)
新型コロナ下におけるニュース番組とメディア・リテラシー──FCTの事例から
<研究ノート> 松本恭幸(武蔵大学)
平和教育、環境教育における博物館の活用促進に向けて
【論稿】
<研究論文> 浅野慎一(神戸大学)
夜間中学とその生徒の史的変遷過程
【書評】
山田泉(元法政大学)
宋美蘭編著『韓国のオルタナティブスクール─子どもの生き方を支える「多様な 学びの保障」へ』、明石書店、2021年2月
井口啓太郎(文部科学省)
生田周二著『子ども・若者支援のパラダイムデザイン─ “第三の領域” と専門性 の構築に向けて─』、かもがわ出版、2021年5月
大多和雅絵(横浜市立学校事務職員)
大重史朗著『多文化共生と夜間中学─在留外国人の教育問題─』、揺籃社、2021 年5月
学会誌を投稿する際の送り状です。
必要事項を記入して添付ファイルで提出してください。
会員の皆様へ
『基礎教育保障学研究』第5号の原稿募集
『基礎教育保障学研究』編集委員会
平素は大変お世話になっております。この度、『基礎教育保障学研究』第5号の原稿 を募集いたします。
第5号 特集テーマ <基礎教育保障とメディア情報リテラシー>
インターネット、そしてソーシャル・メディアが広く普及した現代社会において、メディア・リテラシーや情報リテラシーの習得や教育は、基礎教育保障という観点からも非常に重要な課題となっています。進化したテクノロジーは、その利便性から人々の生活の質を向上させますが、弱者をさらに弱者にし、社会的格差をさらに拡大してしまう危険性も孕んでいます。そうではなく、人々をエンパワーし、世界に平和をもたらすメディア情報リテラシーとは何なのか、基礎教育保障のなかにいかに位置付けるべきか等の研究や教育実践が求められています。
第5号では、「基礎教育保障とメディア情報リテラシー」というテーマで、広く原稿を募集いたします。
また、今年はコロナ禍により、教育をめぐってもさまざまな課題が立ち現れています。そこで、「緊急企画」といたしまして、コロナ禍と教育をテーマとした研究論文や教育実践現場からの報告等も募集することといたします。奮ってのご投稿をお待ちいたします。
特集テーマや緊急企画以外の原稿につきましても、会員の皆様の研究成果や実践の報告、 問題提起など、基礎教育保障をめぐる多様な角度からの論考を広く募集いたします。特に、第5回研究大会のご発表者、ご報告者からのご投稿をお願いいたします。
投稿に関するご案内の文章は、右下のボタンからダウンロードできます。
記
【提出期限】
2021 年 2 月末日締め切り(厳守) 3 月1日以降に届いた分は、第6号への投稿の扱いとします。
【投稿区分について】
学術論文(研究論文、展望論文、実践論文、研究ノート)には査読があります。
報告、評論、資料、書評、その他も募集します。
詳しくは、学会 Web サイトに掲載 の「投稿規程」 、「原稿執筆要項」をご確認願います。
【原稿作成】 2018 年改訂版の「投稿規程」、「原稿執筆要項」を熟読し、厳守願います。
【提出先】 journal@jasbel.org 『基礎教育保障学研究』編集委員会
以 上
『基礎教育保障学研究(The Journal of the JASBEL)』投稿規程(改訂版2018.9)は、右下のボタンからダウンロードできます。 第3号と同様です。
・投稿者要件
・原稿要件
・投稿区分
・査読
・文字数
・執筆上の留意点
『基礎教育保障学研究(The Journal of the JASBEL)』原稿執筆要項(改訂版2018.9)は、右下のボタンからダウンロードできます。
応募の際は、原稿執筆要項を熟読し、上下余白、行数、文字数、フォント、図表、引用などの定められた様式を遵守してください。第3号と同様です。
『基礎教育保障学研究』第5号へ投稿される際には、右下のボタンからワードファイルの書式(投稿用原稿のフォーマット)をダウンロードしてお使いくださると便利です。上下余白、行数、文字数、フォントなどがあらかじめ設定されています。原稿執筆時には、必ず執筆要項も熟読ください。
電子ジャーナル ISSN 2433-3921
『基礎教育保障学研究』 第4号を刊行しました。右下のボタンからダウンロードできます。
記事の個別ダウンロードはこちらをご活用ください。(J-STAGE)

【特集】教育と福祉の連携を求めて
<研究論文> 髙田一宏(大阪大学) 小・中学校における基礎教育保障の課題
<研究論文> 吉田敦彦(大阪府立大学)
〈教育×福祉〉四象限マップの複眼的視座 —教育と福祉の視差を活かした連携のために―
<展望論文> 相良好美(東京大学高大接続研究開発センター)
千葉県における地域日本語支援活動と子ども・若者支援への展開
―『あなたの町の日本語教室』を手がかりに―
<展望論文> 小島祥美(愛知淑徳大学)
愛知県における公立夜間中学の必要性に関する考察
―学齢を超過した外国人青少年に向けた学び直し支援の充実化の視点から―
<実践論文> 宮嶋晴子(九州女子短期大学)
地域活動参加が生活困難を抱えた子育て家庭の幼児にもたらす効果や影響
―公営団地で試みた実践事例をもとに―
【論稿】
<研究ノート> 金侖貞(東京都立大学)・新矢麻紀子(大阪産業大学)
韓国の識字教育における学歴認定制度の評価仕組みの運用と課題
<研究ノート> 碓井健寛(創価大学)
夜間中学のニーズはいかにして測られるべきか?
―神奈川県ニーズ調査を事例として―
<報告> 奥元さえ美(自主夜間中学「えんぴつの会」スタッフ)
自主夜間中学「えんぴつの会」における高齢中国帰国者への日本語教育実践報告
【特別報告】
上杉孝實(基礎教育保障学会会長)・大安喜一(ユネスコ・アジア文化センター)
・ 金侖貞(東京都立大学) ・坂本旬(法政大学)・新矢麻紀子(大阪産業大学)
・ 添田祥史(福岡大学)・棚田洋平(部落解放・人権研究所) ・長岡智寿子(田園調布 学園大学)
・肥後耕生(豊岡短期大学)・森実(大阪教育大学)
日韓基礎教育共同プロジェクトの成果と展望
【特別寄稿】
李智惠(翰林大学校) 韓国の識字教育と識字政策の課題
翻訳:金侖貞(東京都立大学)
千成浩(ノドゥル障碍人夜学) “学びと闘争の空間” としてのノドゥル障碍人夜学
翻訳:肥後耕生(豊岡短期大学)
【書評】
石川敬史(十文字学園女子大学)
渡辺幸倫編著『多文化社会の社会教育─公民館・図書館・博物館がつくる「安心 の居場所」』、明石書店、2019年3月
野山広(国立国語研究所)
万城目正雄・川村千鶴子編著『インタラクティブゼミナール 新しい多文化社会 論-共に拓く共創・協働の時代』、東海大学出版部、2020年2月
『基礎教育保障学研究』第4号へ投稿される際には、右下のボタンからワードファイルの書式(投稿用原稿のフォーマット)をダウンロードしてお使いくださると便利です。上下余白、行数、文字数、フォントなどがあらかじめ設定されています。原稿執筆時には、必ず執筆要項も熟読ください。